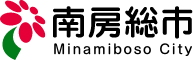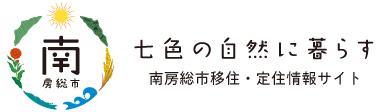後期高齢者医療制度の概要
- 初版公開日:[2022年03月14日]
- 更新日:[2025年7月29日]
- ID:11041
75歳以上の高齢者の方などを対象とした「後期高齢者医療制度」が平成20年4月から施行されています。保険料の決定や医療の給付は千葉県後期高齢者医療広域連合が、保険料の徴収や各種申請の受付は市町村が行います。
詳しくは、次のページをご覧ください。
被保険者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
- 65歳~74歳で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
保険料の納め方
1. 月額1万5千円以上の年金をもらっている方は、次のいずれかの方法によりお支払いいただきます。
- 2か月ごとに支払われる年金からのお支払い。
※後期高齢者医療制度保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合は納付書または口座振替でお支払いいただきます。 - 被保険者本人、世帯主、配偶者等の口座からの「口座振替」によるお支払い。
※市役所及び金融機関でのお手続きが必要です。
2. 月額1万5千円未満の年金をもらっている方は、納付書または口座振替でお支払いいただきます。
保険料
所得に応じ、保険料を負担いただきます。
保険料=1人当りの定額保険料(均等割)+所得に応じた保険料(所得割)
保険料の軽減
- 所得が少ない方の均等割額は、世帯の所得に応じ、7割・5割・2割が軽減されます。
- サラリーマンの夫やお子さんに扶養されていた方は、制度加入後2年を経過する月まで、均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。
医療費の自己負担割合
医療費の自己負担(一部負担金)の割合は、1割、2割または3割です。この自己負担の割合は、前年の所得に応じて判定し、毎年8月1日に見直します。(1月~7月の判定は前々年)
| 自己負担割合 | 所得区分 |
|---|---|
| 1割負担 | 同じ世帯にいる被保険者全員の市町村民税課税所得が28万円未満の被保険者 住民税非課税世帯の被保険者 |
| 2割負担 | 市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者およびその方と同じ世帯にいる被保険者※ |
| 3割負担 | 市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者およびその方と同じ世帯にいる被保険者 |
※被保険者の年金収入+その他の合計所得額が、世帯内に被保険者1人の場合200万円未満、2人の場合は320万円未満の場合は「1割」となります。
自己負担限度額
1か月(同じ月内)の医療費が高額になった場合、下記の自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。
若い世代並みに所得のある方
| 課税所得(※1)による区分 | 外来+入院 |
|---|---|
| 690万円以上の方および同じ世帯の方 (現役並み3) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ●多数回該当(※2)~140,100円 |
| 380万円以上690万円未満の方および同じ世帯の方 (現役並み2) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ●多数回該当(※2)~93,000円 |
| 145万円以上380万円未満の方および同じ世帯の方 (現役並み1) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ●多数回該当(※2)~44,400円 |
※1 地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。
※2 過去12か月以内に3回以上利用者負担が自己負担限度額を超えている場合、4回目から自己負担限度額が減額されることです。
一般的な所得の方および低所得の方
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 一般的な所得のある方 | 18, 000円 年間(8月~翌年7月)144,000円が上限 | 57,600円 多数回該当(※)~44,400円 |
| 低所得の方 2(住民税非課税) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得の方 1(所得なし) | 8,000円 | 15,000円 |
※ 過去12か月以内に3回以上利用者負担が自己負担限度額を超えている場合、4回目から自己負担限度額が減額されることです。
令和6年12月2日以降、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は交付されなくなります
令和6年12月2日以降、限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は新たに交付されなくなります。
〇医療機関での今後のお支払いについて
・マイナ保険証をお持ちの方
各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると、限度額を超える支払が免除されます。
・マイナ保険証をお持ちでない方
オンライン資格確認の仕組みにより、窓口での本人同意で支払いを限度額までにすることができます。
※長期入院該当(食事代・居住費)は申請が必要になります
〇対象者
負担区分Ⅱの方で、申請月から過去12か月の入院日数が91日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含む。)以上とな
った場合、申請月の翌月から該当します。
〇申請に必要な書類
①後期高齢者医療長期入院日数届書
②長期入院が確認できる書類のコピー(入院費の領収書等)
後期高齢者医療長期入院日数届書

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の自己負担額の年間合計(8月から翌年7月末分)が、下記の額を超えた分が払い戻されます。(世帯単位)
| 所得区分 | 合算した限度額 |
|---|---|
課税所得(※) 690万円以上の方および同じ世帯の方 | 212万円 |
課税所得(※)380万円以上690万円未満の方および同じ世帯の方 | 141万円 |
課税所得(※)145万円以上380万円未満の方および同じ世帯の方 | 67万円 |
| 一般的な所得のある方 | 56万円 |
| 低所得の方 2(住民税非課税) | 31万円 |
| 低所得の方 1(所得なし) | 19万円 |
※ 地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。
短期人間ドック受診費用の助成
平成22年度から、短期人間ドック検査費用に対する助成を行います。詳しくは、次のページをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンターの開設
千葉県後期高齢者医療広域連合では、下記のとおりコールセンターを開設しております。マイナンバーカードと後期高齢者医療被保険者証の一体化に関することや後期高齢者医療制度の内容に関することについてお電話でお答えいたします。
〇千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター 0570-066-046(※通話料がかかります)
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
・令和7年6月2日から令和8年3月31日まで(予定)※終了日については、令和7年度の国の補助金等の状況により決定しますので、現時点では予定となります。
〇主な対応業務
・マイナンバーカードと後期高齢者医療被保険者証の一体化に関すること
・被保険者等への各種送付物に関すること
・後期高齢者医療保険料の算定方法等に関すること
・各種保険給付費申請手続き等に関すること
・コールセンター相談窓口で回答することのできない問合わせの関係部署への案内