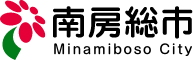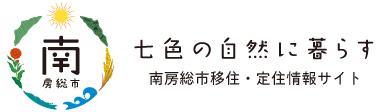児童扶養手当
- 初版公開日:[2025年04月01日]
- 更新日:[2025年4月1日]
- ID:797
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給対象者
次の要件にあてはまる児童を監護している母、または児童を監護し、かつ生計を同じくする父、または父母に代わり児童を養育している人です。
※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が心身に基準以上の障害がある場合は20歳未満まで)です。
1.父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度(労働不能な身体で常時介護を必要とする程度の障害)の障害にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8.未婚の母の児童
9.その他、生まれたときの事情が不明である児童
ただし、上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません。
1.児童が
(1)日本国内に住所がないとき
(2)児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
(3)父または母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合を除く)
※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(頻繁な定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助などが存在すること)をいいます。
2.父母または養育者が
(1)日本国内に住所がないとき
支給額
受給者の前年の所得額に基づき決定します。所得制限があります。所得が制限額以上であるときは、手当の全部または一部が支給されません。また請求者の配偶者や扶養義務者(同居している父母や兄弟姉妹など)の前年の所得が制限額以上である場合は支給されません。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、
所得限度額と第3子以降の加算額が引上げられ、第2子の加算額と同額になりました。
公的年金等を受給している場合は、年金額が手当額より低い場合、その差額分が児童扶養手当として支給されます。
4月支給分(5月支払い分)から支給額が変更します。
| 対象児童数 | 全部支給のとき | 一部支給のとき |
|---|---|---|
| 子どもが1人の場合 | 46,690円 | 11,010円~46,680円 |
| 子ども2人目以降の加算額(1人につき) | 11,030円 | 5,520円~11,020円 |
一部支給の手当額の計算方法
一部支給は、所得に応じて月額11,010円から46,680円(対象児童1人の場合)の間で、10円きざみの額となります。
《児童1人のときの月額》
【計算式】 手当月額=46,680円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0256619
《児童2人のときの月額》
【計算式】 手当月額=11,020円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0039568
※児童3人目以降の加算額は第2子加算額と同じ
※受給者の所得額とは、収入から給与所得控除等の控除を行い、父または母および児童が受け取る養育費の8割相当額を加算した額です。
※所得制限限度額とは、次の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じた額となっています。
※計算式中の「46,680円、11,020円」や 「0.0256619、0.0039568」 は、物価変動により今後改正される場合があります。
支給時期
認定請求した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、それぞれの前月分までを支給します。支給日は各支給月の11日です。
※支給日が土曜日・日曜日・祝日日の場合は、金融機関の前営業日に支給します。
所得による支給制限
所得制限限度額
所得額が下表の限度額以上ある場合、その年の11月分から翌年の10月分までの手当は、全部または一部支給停止となります。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、
所得限度額が引き上げられています。(扶養義務者の変更はありません。)
| 扶養親族等の数 | 父、母または養育者 (全部支給) | 父、母または養育者 (一部支給) | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
| 4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
| 5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。
- 本人の場合は、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円
- 孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
<所得額の計算方法>
所得額 = (年間収入金額+父または母および児童が受け取る養育費の8割)-必要経費
-80,000円(社会保険料共通控除)-その他の諸控除(地方税法上の控除について定められた額)
【参考】給与収入に換算した場合の所得制限限度額
| 扶養親族などの数 | 父、母または養育者 (全部支給) | 父、母または養育者 (一部支給) | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 142万円 | 334万3千円 | 372万5千円 |
| 1人 | 190万円 | 385万円 | 420万円 |
| 2人 | 244万3千円 | 432万5千円 | 467万5千円 |
| 3人 | 298万6千円 | 480万円 | 515万円 |
| 4人 | 352万9千円 | 527万5千円 | 562万5千円 |
| 5人 | 401万3千円 | 575万円 | 610万円 |
※上の表はあくまでも目安であり、実際は地方税法上の控除後の所得額で決定されます。
一部支給停止措置
受給資格者が、次のどちらかに該当する場合は手当の2分の1が支給停止(減額)されます。対象となる方には事前にこれに関する通知を送付します。
- 手当の支給開始月の初日から起算して5年が経過した
- 手当の支給要件に該当した月の初日から起算して7年が経過した
※平成15年4月1日現在手当を受給している方は、平成15年4月1日が起算日となります。また、認定請求時に3歳未満の児童を監護する受給資格者は
対象児童が3歳に達した月の翌月が起算日となります。
ただし、下記の事由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および添付書類を提出した場合は、一部支給停止措置の適用除外となります。
【一部支給停止適用除外事由】
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または疾病等により就業することが困難である
- 受給資格者が監護する子どもまたは親族が、障害、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である
児童扶養手当の手続きについて
はじめに行うこと
「認定請求」の手続きが必要です。事前に教育委員会子ども教育課へお問い合わせの上、必要書類をそろえて提出してください。
続けて手当を受ける場合
毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認し、また、8月分からの支給額を決定するためのものです(前年の手当が全額支給停止の方も含みます)。
この届の提出がないと8月分以降の手当が受けられなくなります。また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
届出の内容が変わったとき
以下のときは、すみやかに届出をしてください。
- 対象児童の増減があったとき
- 氏名や住所、振込指定口座が変わるとき
- 受給者が死亡したとき
- 手当証書をなくしたり、破損したとき
- 障害認定(父障害で受給される方)の期限が設定されているとき
- 受給者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟など)と同居するようになったとき
- 受給資格がなくなるとき
受給者である父または母が婚姻したとき(「事実上の婚姻」を含みます)
遺棄していた父または母から連絡があったとき
拘禁されていた父または母が出所してきたとき
児童が社会福祉施設に入所したとき
父、母、または養育者が、児童を監護(養育)しなくなったとき
対象児童が死亡したとき
受給者または児童が公的年金を受給できるとき
対象児童が満18歳に達する日以降の3月31日を経過したとき
資格がなくなっているにもかかわらず届出をしないで手当を受給していると、 資格がなくなった翌月からの手当はさかのぼって全額返還していただきます。
また、偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、 3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
お問い合わせ
電話: 0470(46)2936 ファクス: 0470(46)4059