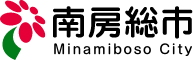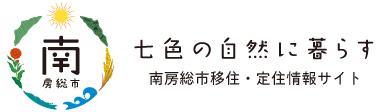予防接種
- 初版公開日:[2023年04月01日]
- 更新日:[2025年4月1日]
- ID:14384
予防接種が行われる病気は、そのほとんどは感染力が強く、一度発症すると有効な治療法がなかったり、あるいは死亡率が高かったり、後遺症を残す頻度が高いなど、重篤な疾患が多く含まれています。予防接種はそれを受けることによって、それらの被害を避けることができます。
また予防接種は、お子さんを病気から守るのと同時に、お子さんの家族や友人、将来生まれる子どもたちの健康をも守ることになります。
予防接種に対する正しい理解のもとで、お子さんの健康にお役立てください。
お知らせ
日本脳炎予防接種の特例対象者について
平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれの人で接種機会を逃した人について、20歳になるまでの間、不足回数分を公費で接種することができます。
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで20歳未満の人
20歳未満までの間、接種できます。1期が終了していない人は、まず、1期から接種を受けてください。
接種回数と接種間隔は表のとおりです。
| 既に接種した回数 | 接種回数 (全4回) | 接種間隔 |
|---|---|---|
| 全く受けて いない人 | 残り4回 (1期3回、2期1回) | 1回目の接種後6日以上(標準的には28日まで)の間隔をあけて2回目を接種し、その後6か月以上(標準的にはおおむね1年)の間隔をあけて3回目を接種します。 4回目(2期接種に相当)の接種は、9歳以上の人に対し、3回目の接種後6日以上の間隔をあけて接種します。(※) |
| 1回接種を 受けた人 | 残り3回 (1期2回、2期1回) | 2回目と3回目は6日以上の間隔をあけて接種します。 4回目(2期接種に相当)の接種は、9歳以上の人に対し、3回目の接種後6日以上の間隔をあけて接種します。(※) |
| 2回接種を 受けた人 | 残り2回 (1期1回、2期1回) | 3回目と4回目(2期接種に相当)は6日以上の間隔をあけて接種します。 ただし、4回目(2期接種に相当)の接種については9歳以上の人に対して行います。(※) |
| 3回接種を 受けた人 | 残り1回 (2期1回) | 4回目(2期接種に相当)の接種を行います。 ただし、9歳以上の人に限ります。(※) |
※ 2期は1期終了後、9歳以上で6日以上の間隔をおいて受けることができますが、通常は1期接種の終了後、おおむね5年の間隔をおいて接種することが望ましいとされています。
麻しん風しん混合予防接種2期について
令和7年度の麻しん風しん混合予防接種2期の対象は平成31年4月2日生まれ~令和2年4月1日生まれです。
接種期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日です。
対象となるお子さんには令和7年3月末に個人通知していますので、体調の良い時に早めに接種を受けましょう。
なお、通知が届いていない場合や転入された人は子ども家庭支援室へ連絡してださい。
二種混合(ジフテリア・破傷風混合)予防接種2期について
令和7年度の二種混合(ジフテリア・破傷風混合)予防接種2期の対象は平成25年4月2日生まれ~平成26年4月1日生まれです。
望ましい接種期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日です。
対象となるお子さんに令和7年3月末に個人通知していますので、体調の良い時に早めに接種を受けましょう。
なお、通知が届いていない場合や転入された人は子ども家庭支援室へ連絡してください。
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン
対象者(小学校6年生から高校1年生相当まで)
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの女子
令和7年度対象者 平成21年4月2日生まれから平成26年4月1日生まれまでの女子
対象者(積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人 キャッチアップ接種経過措置)
平成9年4月2日生まれから平成21年4月1日生まれまでの女子のうち
令和4年度から6年度までに1回以上接種した方は、令和7年4月以降も残りの接種を公費で受けられることになりました。
接種期間は令和8年3月31日までです。
接種について
平成25年6月14日厚生労働省からの通知において、ヒトパピローマ感染症予防接種後から持続的な痛みが発生したとの報告があり、ワクチンとの関連性を否定できないことから、当分の間は、接種の積極的勧奨を差控えていましたが、令和3年11月26日厚生労働省の通知により、接種勧奨を再開することになりました。又、積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した人に対しては、公平な接種機会を確保する観点から、令和4年度から令和6年度までキャッチアップ接種(従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うこと)を実施しておりましたが、令和6年夏以降の大幅な需要増により経過措置が設けられました。
令和7年4月、中学1年生女子の未接種者に個人通知します。
※上記以外で接種を希望する場合や転入者で希望する場合、予診票の再発行希望は子ども家庭支援室へ連絡してください。
下記の厚生労働省作成のリーフレットを読み、ワクチンの有効性と接種による副反応を理解した上で、接種を受けるようにしてください。また、気になることがあれば接種前に医師と相談するようにしましょう。
ワクチンの種類と接種間隔
現在、定期接種として利用できるHPVワクチンは、以下の3種類があります。令和5年4月から新たにシルガード9 9価ワクチンが定期接種に使用できるようになりました。
●サーバリックス 2価 (16型・18型)
●ガーダシル 4価 (6型・11型・16型・18型) ※6型・11型は尖圭コンジローマの主要な原因 ●シルガード9 9価 (6型・11型・16型・18型・31型・33型・45型・52型・58型)
ただし、接種を受けるにあたっては、同一のワクチンで接種を受ける必要があるため、どちらのワクチンで接種を受けるかは医師とご相談ください。
※どの種類のワクチンを取り扱っているかは、希望する実施医療機関に直接問い合わせてください。
※接種の途中で妊娠した場合には、接種は継続できません。その後の接種については医師にご相談ください。
| ワクチン名 | 接種回数 | 接種間隔 |
|---|---|---|
| サーバリックス (2価) | 3回 | 2回目:1回目の接種から1か月の間隔をおいて1回接種 ※上記間隔で接種できない場合 |
ガーダシル | 3回 | 2回目:1回目の接種から2か月の間隔をおいて1回接種 ※上記間隔で接種できない場合 |
シルガード9 | 2回 | 15歳になるまでに1回目の接種を受ける場合 2回目:1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種 ※少なくとも1回目から5か月以上あけます。5か月未満の場合や1回目が15歳以上の場合は3回接種 |
シルガード9
| 3回 | 2回目:1回目の接種から2か月の間隔をおいて1回接種 ※上記間隔で接種できない場合 |
厚生労働省ホームページ
HPVワクチンリーフレットはこちらから
副反応について
HPVワクチンだけでなく、他の予防接種でも同等の頻度で副反応が発生します。
主な副反応は、接種部位の疼痛、発赤、腫脹です。他に発熱、頭痛、胃腸障害、筋肉・関節の痛みなどの全身反応もあります。
重い副反応として、まれにアナフィラキシー反応などの過敏症反応、ギランバレー症候群、血小板減少性紫斑病、急性散在性脳脊髄炎等が現れることがあります。
万が一、注射した場所に限らず、痛みやしびれ、脱力などが起こり、長く続く場合には、医師にご相談ください。
異なるワクチンの接種間隔について
令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔が一部変更されました。
従来、異なるワクチンを接種する場合、接種してから次のワクチンを接種するまでの間隔は、生ワクチンなら接種後27日以上、不活化ワクチンなら6日以上あけることが規定されていました。
令和2年10月1日の予防接種法改正で接種間隔の制限の一部が緩和され、今後は注射の生ワクチンから注射の生ワクチン間について27日以上の間隔をあけることとなり、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
ただし、今回の改正はあくまでも異なるワクチンを接種する場合の間隔で、同じ種類のワクチンを複数回接種する際の接種間隔は従来通りとなりますのでご注意ください。
★厚生労働省ホームページ:ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ★(別ウインドウで開く)
予防接種の通知時期と受け方について
それぞれの予防接種には、接種対象年齢が決まっています。
お子さんが対象年齢になると、市から予診票を郵送します。
初めての予防接種予診票の通知のときには、「予防接種と子どもの健康」という冊子も送付しています。
この冊子は、これから受ける予防接種について、保護者の人が正しい知識を持って安全に受けられるように配慮されて作られたものです。
この冊子をよく読んで、内容を理解した上で予防接種を受けるようにしましょう。
予防接種スケジュール
平成25年1月30日より、長期にわたる重篤な疾患等のため、定期接種を受けられなかったお子さんについて特例措置が設けられました。
詳しくは、「長期にわたり療養を必要とする疾患にかかったこと等により定期予防接種の機会を逃した人へ」をご覧ください。
予防接種の通知時期と接種間隔について

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
予防接種を安心して受けていただくために
厚生労働省が各ワクチンのはなしをまとめ、「キョウコノワクチン」というリーフレットを作成しています。
接種前にお読みいただき、参考にしてください。
ヒブ
小児用肺炎球菌
DPT‐IPV(百日せき・ジフテリア・破傷風・ポリオ4種混合)ワクチン
BCG(結核)ワクチン
MR(麻しん・風しん混合)ワクチン
日本脳炎ワクチン
水痘ワクチン
予防接種実施医療機関
市内の定期予防接種実施医療機関の一覧になります。
事前に医療機関へ予約してください。
定期予防接種実施医療機関一覧

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
南房総市以外(千葉県内)で予防接種を希望する人へ
千葉県内では、市外の医療機関でも予防接種が受けられる「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度」を実施しています。県内の相互乗り入れ接種協力医療機関で予防接種が受けられます。
≪対象者≫
1.かかりつけ医が市外にいる人
2.出産などで里帰りしているなどやむを得ない事情により、南房総市内で予防接種を受けることが困難な人
≪手続き方法≫
1.接種希望者は、千葉県医師会ホームページ(別ウインドウで開く)または子ども家庭支援室へ問い合わせをして、相互乗り入れ接種協力医療機関になっていることを確認してください。
2.医療機関に接種の予約をし、予防接種を受けてください。
3.予診票は南房総市のものを使用してください。
千葉県外で予防接種を希望する人へ(依頼書発行・償還払い)
この制度は、療養等のために千葉県外等で定期予防接種を受けた場合に、費用負担(自己負担)が生じた方に対して、南房総市が契約している委託料金を上限に接種費用を助成するものです。
≪対象者≫
1.療養その他の理由で、千葉県外の医療機関で定期予防接種を受けた人
2.他の市区町村が実施する定期予防接種を受けた方で、予防接種に要する費用を全部支払った人
3.その他市長が認める人
上記の対象となる人は、事前に子ども家庭支援室へ定期予防接種を受ける旨を連絡してください。
予防接種健康被害救済制度について
南房総市の予防接種によって健康被害が起こったときの救済は、定期予防接種による健康被害、任意予防接種による健康被害の制度があります。
定期予防接種(ロタウイルス感染症・B型肝炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・五種混合・四種混合・BCG・三種混合・二種混合・不活化ポリオ・麻しん風しん混合・日本脳炎・子宮頸がんワクチン)による健康被害は、予防接種法により当該予防接種と因果関係がある旨を厚生労働省が認定した場合に市が救済します。
任意予防接種(定期予防接種以外の予防接種または定期予防接種で接種対象者以外の予防接種)による健康被害は、独立行 政法人医薬品医療機器総合機構法により救済されます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師及び子ども家庭支援室へ相談してください。
予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省作成リーフレット)
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種の機会を逸した人へ
平成25年1月30日より、長期にわたる重篤な疾患等のため、定期接種を受けられなかったお子さんについて特例措置が設けられました。詳しくは、下記のファイルをご覧ください。
対象者及び申請方法について
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会子ども教育課 子ども家庭支援室(丸山分庁舎)
住所: 南房総市岩糸2489番地
電話: 0470(46)2957
ファックス: 0470(46)4059
電話番号のかけ間違いにご注意ください!