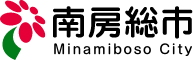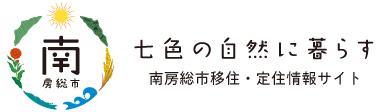たかべのふるさとどぶろく特区
- 初版公開日:[2023年01月20日]
- 更新日:[2023年1月25日]
- ID:17969
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
南房総市全域における「どぶろく特区」の認定
平成24年11月30日付けで、構造改革特別区域法に基づく構造改革特区「たかべのふるさとどぶろく特区」が内閣総理大臣の認定を受けました。
概要
本市には、日本で唯一、料理の祖神を祀る高家神社が鎮座しており、民宿等は神社に伝わる「古式料理」や豊かな地元産物を使った料理を宿泊客に提供するなど、伝統継承と観光客の呼込みに努めてきました。しかしながら、近年の旅行スタイルの多様化や道路網整備等により宿泊客数が減少、合わせて宿泊業数も減少しています。
そこで、民宿等も行う農家自らが生産した「安心・安全な」古代米等を原料とする濁酒と料理を共に提供し、歴史、安全性の面でも高付加価値化に努め、新たなブランドとして、交流人口の増加を図り、地域経済活性化を目指します。
区域
南房総市の全域
特例措置の内容
濁酒の製造免許を受けるためには、酒税法の規定により、通常は「最低製造数量基準(年間の見込み製造数量が6キロリットルに達していること)を満たすこと」が必要となります。
特区に認定されたことにより、上記の最低製造数量基準が緩和されます。特区の区域内において、農園レストランなどを営む農業者自らが濁酒を製造する場合は、最低製造数量基準未満であっても製造免許の取得が可能となります。
なお、特区において特例措置の適用を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
- 濁酒を製造する者は、農家民宿や農家レストランなど、酒類を自己の営業場において飲用に供する業(旅館、料理飲食店など)を併せて営む農業者であること
- 市内に所在する自己の酒類の製造場において、自ら生産した米を原料として濁酒を製造すること
- 製造する酒類は、構造改革特別区域法に定められている濁酒に限ること
留意事項
- 特例措置を受けて製造された濁酒は、自己の営業場で飲用に供する場合や酒類製造者がその免許を受けた製造場において販売する場合に活用が限られます。
- 濁酒を製造しようとする場合、酒類の製造免許を取得することが必要であり、特区内であっても製造免許を受けなければ、濁酒を製造することはできません。
- 特例措置により酒類製造免許を受けた人は、酒税法の規定を守り、酒税法上の最低製造数量基準以外の要件を満たす必要があります。これに違反すると、罰則や免許の取り消しの対象となります。
- 製造免許を取得した者は、酒税法の規定に基づき、酒税額などの申告、納税および酒類の製造、移出などに関する記帳などを行う必要があります。
なお、製造免許の申請手続きなどについては、管轄する千葉東税務署(電話番号:043-225-6811)に問い合わせてください。